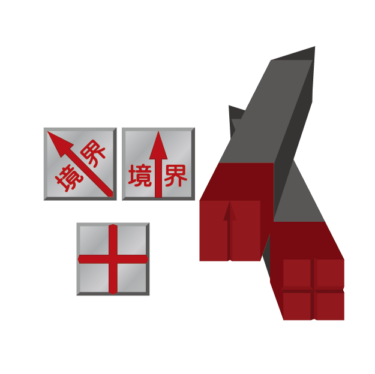ご存知でしたか?
地代(じだい・ちだい)の計算方法には決まりがありません。
毎月発生している地代は、何を根拠に計算されたものなのでしょうか?
果たして適正なのでしょうか?
今回は7つの計算式と具体例を示しながら
得しているのは地主さん?
それとも借地人さん?
このどちらかを明確にしていきましょう。
投資家の方も必見ですよ。
7つの地代の計算式で実際に計算してみましょう!
(1) 公租公課倍率法

土地にかかる税金としては固定資産税と都市計画税の二つがありますね。
これらの税額は毎年送られてくる固定資産税納税通知書を見れば分かります。
この通知書に記されている年額から固定資産税等の月額を割り出し、一定割合をかければいわゆる地代相場が分かります。
首都圏や大都市の住宅地であれば、税額の3倍から5倍程度を地代目安とします。
一方で、同じエリアでも商業地であれば5倍から8倍にすることで、大まかな相場を確認できます。
住宅地よりも商業地の方が資産価値と賃料が高くなる傾向がありますので、やはり地代を計算する場合も、その差をつけることが重要です。
具体例
『固定資産税と都市計画税の合計額が年間20万円の土地の場合』
・住宅地であれば5万円~8万3千円程度
・商業地であれば8万3千円~13万3千円程度
この計算方法の注意点としては、これはあくまでも大まかな相場を見るに過ぎないということですね。
税額の3倍から8倍にすれば、収支のバランスを取ることができますが、それだけでは土地の実際の価値に見合った地代が出ないこともあります。
そのため、この方法では広い幅で相場を見るに留めて、他の方法を使うことでさらに額の範囲を絞っていくことが重要ですよ。
公租公課を基準にして地代を計算するという方法は、借地人に説明しやすいのが便利です。
特に地代の変更をしたい時には、借地人はどうしてこの地代が出てきたのか、と尋ねてくることが多いので、その理由となるものを地主として示す必要があります。
その点、税金額をベースにした地代計算は、いわば行政機関のお墨付きがあるようなものですので、説得しやすいんですね。
国が税金を上げたから、地主としても上げざるを得ないと言えるということですね。
また、土地のみの賃貸借では税金以外のコストはほぼかからないという事情がありますので、税金額と地代を連動させることで、収支バランスを安定させられるというメリットも生まれます。
支出に対しての割合で収入額を決められるので、常に利益率が同じで推移していくことになるからです。
(2)路線価を基準にする

国や自治体が所有している道路、つまり国道や県道、市道には、それぞれの資産価値に応じて金額が付けられているんですね。
そこで、ある土地がいくらの価値が付いている道路に沿っているかが分れば、国が見ている土地の資産価値がいくらになるかが分かるということになりますね。
この路線価は、国税庁が固定資産税を算出するのに用いている公式な基準でもあります。
路線価が上昇すれば、それに伴って固定資産税も高くなるというわけですね。
それだけ、公的な数字で地代を決める際の基準として確かであるというメリットがあります。
路線価は公表されていて誰でも見られますので、まずは国税庁の路線価が掲載されているページにアクセスします。
貸したいと思っている土地を地図上もしくはリスト上で見つけて、そこに記載されている路線価を確認します。
路線価は「1000B」とか「500C」といった表記がなされていることに気付くはずです。
この数字が路線価を示していて、500は1平方メートル当たりの額が50万円であるということですね。
「1000」となっていれば100万円となりますね。
そして、自分の土地の面積をこの単価にかけます。
200平米の土地で単価100万円であれば、2億円です。
ここでの注意点は、路線価というのは実勢価格よりも低く設定されているということです。
実際に取引される価格よりも8割程度に設定されているんですね。
そのため、「路線価×1.25」で実勢価格が出てきます。
このケースであれば、「20,000×1.25」で2億5,000万円が実勢価格ということになりますね。
これで土地を売買する時の大まかな価格を知ることができましたので、後はそれに基づいて年間地代を計算します。
地代は、実勢価格の1パーセントから1.5パーセントくらいが相場です。
そのため、250万円~375万円程度が年間地代としてふさわしいと分かるわけですね。
具体例
『1平米あたり100万円の相続税路線価が設定されているエリアの200平米の土地の場合』
100万円×200平米×1.25×0.01~0.015=250万円~375万円と計算されます。
(3) 積算法

一方でこの積算方法というのは、収支そのものに注目して計算するというものです。
土地を貸すことによって得たい利回りを決めて、そこから地代を割り出します。
つまり、自分がいくらの収入を得たいかという観点で計算するんですね。
その計算方法は、「土地買取価格×期待利回り+固定資産税・都市計画税」というものです。
期待利回りとは、投資用の土地を購入するに使った金額に対してどのくらいの収益を得られるかということを示す数値ですね。
商業地や住宅地かなどの要素によっても変わってきますが、土地を貸す場合は年間で2パーセントが相場となっています。
期待利回りを基にして配当の額も予測することができます。
たとえば、5,000万円で購入した土地で期待利回りが2パーセントとすれば、配当は100万円となりますね。
これでおおよその収入見込みと収支割合を検討することができます。
この積算法を使うことによって、税金という支出に加えて収益を入れることができますので、実際の地代に近い数値を出しやすくなるのがメリットですね。
具体例
『土地価格が5,000万円、固定資産税・都市計画税の年額が20万円の土地の場合』
5,000万円×2%+20万円=120万円
積算法による年間相当地代は120万円と計算されます。
こうすることで、しっかりと利益も確保できますし、ランニングコストをカバーできますので安定した運用ができることになるんですね。
ただし、この方法だと上記のような方法、税金額や路線価を基にした計算とは数字が異なることも多々あります。
土地の買い取り価格が積算法ではベースになっているからです。
特に、土地を購入してから年数が経っていると、現在の実勢価格とはかけ離れていることも多いので注意が必要ですよ。
より最近購入した場合には、路線価を使った計算方法と近くなり相場を見やすくなりますので有効な手段となります。
少なくてもある程度年数が経ってからの、地代変更の際には使いづらい計算方法と言えるでしょう。
(4) 賃貸事例比較法

比較対象としてはできるだけたくさんの物件をピックアップしてチェックするのがベストです。
似ている条件ごとにリスト化すると、より平均的な地代を出しやすくなります。
土地の面積や角地かどうか、道路に面しているか、近くに店舗や駅があるかどうかなどの条件によって比較することができますね。
また、商業地や住宅密集地などの地域特性も比較する上で確認したい点となります。
理想的なのは、自分の土地と似た条件のものが近隣にあることです。
その土地ではどのくらいの地代となっているかを知ることで、より実情に合った額を算出することができるというわけですね。
賃貸事例比較法のメリットは、より現実的な計算ができるということですね。
また、借地人に対して金額の根拠を提示しやすいというのも都合がいいですね。
同じエリアの土地もこの金額なので妥当であると言えるからです。
トラブルを回避する点でも、この計算はしておいた方が良いでしょう。
しかし、近隣に比較対象となる事例が少ない点は大きなマイナス面でもあり、一方で、周りの物件が値上げをしない限りは、自分のところも高い額を提示しづらいなどのデメリットもありますので、慎重に判断すべきですね。
地代は借地権との関係で、簡単に額を上げるというわけにはいかないため、昔からの借地が多い地域では、現在の不動産価値に比べると割安感が出ているところもあります。
不動産投資に慣れている人は、こうしたエリアを狙って借地権を得ようとするケースもありますので、周囲の賃貸額の比較だけでは適正な額を出しづらく、交渉も難しくなってしまうことがあるんですね。
こうしたことから、参考のために賃貸事例比較法を使って計算をするのは必要なことですが、適正な不動産価値評価になっているかどうかを確かめるためにも、路線価による計算なども同時に行うべきですね。
具体例
『対象地の土地面積は100平米。近隣に地代賃料の以下3つが存在する』
①80平米で年間地代80万円 ※1万円/平米
②90平米で年間地代100万円 ※1.1万円/平米
③100平米で年間地代90万円 ※0.9万円/平米
①~③の平均が1平方メートルあたり10,037円ですので、対象地の年間の地代は1,003,700円と計算できます。
こうすることで、現実を反映させながらも相場感のある地代を割り出すことができるというわけですね。
(5) スライド法

現在の地代に変動率をかけることによって、いわゆる時価を求めることができるというものです。
具体的には、「今の地代額×変動率+公租公課」という計算が成り立ちます。
具体例
『現在の年間地代が100万円で年間の公租公課が20万円の場合』
(100万円ー20万円)×1.2+20万円
年間の相当な地代額は116万円と計算できます。
※公租公課とは固定資産税・都市計画税のことを指します
変動率は物価変動指数などを使うことが多く、当初の地代との差を簡単に確認できるのがメリットです。
特に、エリア周辺で都市開発がなされているといった不動産価値を変動させる状況が生じている時に、この計算方法で見直しをするといいですね。
ただし、変動率は借地人から見ると根拠として若干あいまいなところもありますし、これで計算をすると周辺エリアにある物件との差が出てしまうことも起こりえるんですね。
そのため、スライド法を使う際には、現在の地代が適正なものとなっているかどうかを判断するために用いるのがベストです。
この計算方法を根拠にして地代交渉をすると、納得してもらうことが難しいこともありますので、あくまでも自分の中での分析のために使うという考え方が合っているとも言えますね。
(6) 収益分析法

たとえば、ブランドの路面店を出している場合、その土地でなければどのくらいの損失があるかというのを算出して、土地の価値を金額で示すことができます。
明確な数字を出すのが難しいこともあり、借地人からの納得を得づらいこともありますが、地代を計算する上での基本となる考え方でもありますので、覚えておくと役立ちますよ。
具体例
『物件価格が2,000万円、投資利回りが10%、必要諸経費が20万円の場合』
2,000万円×0.1+20万円
相当な地代額は年間で220万円と計算できます。
このように、底地権者というよりも借地人目線で求める計算方法で、不動産としての価値を立地条件から割り出すことができるのが特徴です。
借地人がどのように使うかによって、営業利益が変わってくるものでもありますので、客観性を出すために他の方法と組み合わせて使う方が信頼性があります。
(7) 差額配分法

当初の契約時の金額と、現在の資産価値の上昇率もしくは下降率を見て、どのくらいの差があるかを求めます。
そしてその差額分を、地主と借地人に配分するものです。
配分率の相場は2分の1または3分の1ですね。
つまりは、適正な新規賃料と従前の賃料との差額部分を算出しその差額分の2分の1~3分の1を貸主・借主に配分するといった考え方です。
従って上記の差額とは正常賃料ー実際賃料とも言い換えることができます。
それにより、当初と現在の間に生じている差額を新たな地代額に反映させることになります。
具体例
『現行の地代が年間120万円、適正賃料が140万円、配分率が2分の1の場合』
120万円+(20万円×0.5)=130万円
相当な年間地代額は130万円と計算されます。
場合によっては、地代額を下げざるを得ないこともあります。
契約の存続期間やこれからどのくらい借り続けるかによっても変わってきますので、時間的な要素も同時に考慮する必要がありますね。
そもそも地代とは?

改めておさらいしておきましょう。笑
底地と借地で言えば、土地の賃貸借契約や借地契約において、借主である借地人が貸主である底地人「地主」に支払う賃料のことですね
地主目線で言えば、土地を貸して賃料収入を得るのは、安定した不動産投資の手法で、いろいろなメリットがあります。
利益を確実に上げるためには、地代の計算がとても重要になります。
まとめ

いかがでしたか?
7つある地代の計算式を列挙してみました。
実際の地代の値上げ交渉や値下げ交渉などの場面においては、さすがに不動産鑑定士の手を借りるなどして慎重に行うのが良いでしょう。
少しだけ上述した通り、土地の賃貸借は貸し手の地主よりも借り手の借地人の方が法的に強い傾向があります。
時とともに経済が発展、貨幣価値も上昇しているのにも拘らず、古い時代に結ばれた地代が今もなお適用されているケースも珍しくありません。
当コンテンツを機に地代を見直してみるのも良いと思いますよ。
最後までお読みいただき有難うございました。
土地を購入して所有権を得るよりも、初期投資金額がかなり低いというものも魅力な借地権。借地権を使った不動産投資は様々な地域、物件で行われるようになっています。しかし、借地権は所有権の不動産には不必要なランニングコス[…]
借地権投資はコストが抑えられる効率的な投資手法として注目を集めております。物件にもよりますが、所有権と比べ平均で2~3%の高利回りを得れることでしょう。また、立地も都会のど真ん中に存在すること[…]
借地権付き建物は売却して現金に換金することのできる強い権利形態です。借地を第三者に売ることで利益を得ることもできます。しかし実務において、これすら知らない借地人さんが実に多いのだなぁと感じる今日この頃でもあります[…]
借地権の買取は専門仲介にお任せください!

他社で断られた借地もまずはご相談!
底地・借地の専門家・どこよりも高い売却を実現・安心の買取保証付き。
業界トップクラスの高額売却を実現/底地の取引実績も豊富。
無料査定を依頼する

 クリックで拡大
クリックで拡大